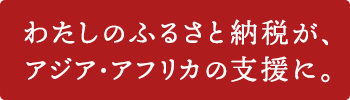【台湾】国境を越えて、ひとり一人に未来をつくる力がある
【台湾レポート/2025年8月】

テラ・ルネッサンスと共にカンボジアへ
今年8月、私は弊会のインターン生として、職員の方々および台湾から参加した8名の若者と共に、台湾のグローバル人財育成プログラムの一環であるカンボジアツアーに参加しました。今回の内容は台湾で初めて台湾の学生をテラ・ルネッサンスの活動拠点に訪れる初めての試みであり、特別な意義をもつものでした。
出発直前、カンボジアとタイの国境で軍事衝突が発生し、不安が広がりました。台湾担当の職員香葉村からは、出発の一週間前には延期や中止が真剣に検討されたことを聞きましたが、幸い衝突は限定的に収まり、私たちは無事に旅立つことができました。今回の衝突は、深い傷を負った被害者に再び刃を突き立てるような出来事であり、致命的ではないにせよ、新たな痛みと癒えにくい傷を残しました。
スタディツアーでは、プノンペンのトゥールスレン虐殺博物館(旧S21収容所)や「チュンエク殺害原野」を訪れた際、重苦しい歴史の現実に直面しました。クメール・ルージュによる4年間の恐怖政治がもたらした大虐殺と非人道的行為、さらにその後の米国・ベトナムによる侵攻や度重なる爆撃は、この輝かしい文明の地を徹底的に荒廃させました。話に聞いたことはあっても、三階建ての建物を埋め尽くす頭蓋骨の山を目の前にしたとき、初めて「命の重み」と戦争・苦難の現実を全身で感じ取ることができました。
.png)
軍事衝突が再び発生すると、噂や偽情報が瞬時に拡散し、恐怖が広がりました。街頭に掲げられていた「#Cambodiawantpeace」というスローガンが示すように、長年の内戦で故郷を失った経験をもつカンボジア人は、戦争の代償を深く理解しており、誰一人としてその再来を望んでいません。現地ガイドや訓練センターで暮らす住民、そしてカンボジア駐在の江角や津田との交流を通じ、今回の衝突とその影響について理解を深めることができました。
.png)
タイとカンボジアは地理的に近く、文化や食習慣も類似しています。しかし、より高い収入水準を誇るタイには多くのカンボジア人労働者が流入しています。今回の衝突は国境住民の避難を引き起こしただけでなく、SNS上で拡散した「カンボジア人労働者がタイで不当な扱いを受けている」といった情報や、カンボジア政府による「タイ側の挑発が原因だ」との非難によって、数十万人もの出稼ぎ労働者が帰国する事態となりました。政府は新たな雇用の提供を約束しましたが、短期間での実現は難しく、数年を要する可能性もあります。
この大規模な人口移動は雇用問題にとどまらず、教育体制にも大きな負担を与えています。特に労働者の子どもたちの教育は、喫緊の課題だと感じました。これらの問題が短期間で解決されるとは思えません。経済力や統治能力に限りがあるカンボジア政府にとって、外国からの投資や国際NGOといった外部の協力こそが、持続的な解決への糸口となるでしょう。
このような厳しい状況の中で、テラルネはどのような役割を果たせるのでしょうか。今回のツアーを通じて、私は「一人ひとりが未来を創る力を持っている」というテラルネの理念を、実感を伴って理解することができました。
バッタンバンにある農業訓練センターでは、約10名の若者が私たちと寝食を共にしました。彼らはまだ若いにもかかわらず、食事の準備や日常の世話を担っていました。テラルネの日本人職員タイさんから、彼らの多くが困難な家庭環境にあり、国境近くの村で職員と出会ったことをきっかけにセンターに入ったことを知りました。
センターでは宿泊と食事が無償で提供され、農業技術や文化的知識が学べます。給料はありませんが、ときに少額のお小遣いを受け取ることもあるそうです。彼らは農業に加えて文化知識を学び(意外と、英語、中国語、日本語喋れる人が何人もいました)、その知識を未来を築く力へと変えようとしています。外の世界と触れ合うことで、自分の理想をより鮮明に描き、国の将来に思いを馳せている姿は印象的でした。そして交流の中で何度も耳にしたのは「カンボジアはとても美しい国だ」という言葉でした。彼らが将来、バッタンバン、さらにはカンボジア全体を変えていく存在になると確信しています。
.png)
台湾から参加した8名の若者たちも、高校生から大学生、社会人まで幅広く、それぞれのチームで独自の人道支援計画を立てました。議論や発表を通じて、私は助言を与える立場でありながら、彼らの柔軟な発想から多くを学びました。特に「移動図書館」計画は、学習資源に乏しい地域の若者を支援し、他のNGOとの連携も視野に入れた意欲的なものでした。予算や持続性に課題は残るものの、その具体性や実現可能性は期待以上のものであり、現地職員や住民との協力を通じて、将来の発展を支える確かな力となるでしょう。
.png)
バッタンバンという地名には古い伝説があります。「បាត់」(batt=失う)と「ដំបង」(dam-bong=杖や神木)に由来し、かつて神杖を得た者がこの地を治めたが、杖を失って力を失ったと伝えられています。現在も交差点には神杖を掲げる大きな像が立っています。この未来を象徴する杖は、神や支配者だけのものではなく、地元の人々一人ひとりが持つべきものなのです。テラルネの役割は、まさに人々がこの「杖」を取り戻し、それを活かしてより良い未来を創れるよう支えることだと思います。
.png)
今回のツアーで学んだ最も大きなことは、世界平和の実現は国家間の条約や国際会議だけで達成されるものではないということです。大切なのは、市民一人ひとりが「未来を創る力」を信じ、その力を発揮することです。国際協力を通じて「杖」を地域の人々に返すことこそ、誰もが関わることのできる、そして最も確かな平和への道ではないでしょうか。人々は単なる受け身の被害者ではなく、むしろ未来を築き、世界平和を推し進める主体であるべきなのです。
アメリカの人類学者マーガレット・ミードはこう述べています。
「少数の思慮深く、確固たる意志を持った市民が世界を変えることを疑ってはならない。実際、それこそが世界を変えてきた唯一の方法なのだ。」
この言葉のとおり、未来を創ろうとする市民の小さな輪は、テラルネや他の活動によって着実に広がり続けています。そしていつの日か、それは国境を越え、未来を信じるすべての人々を包み込んでいくのだと、私は強く信じています。
---------------------------
記事執筆/
国際運動推進部 台湾事業
インターン生 李 純幻