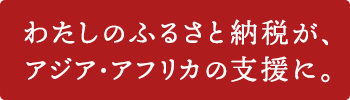【2024年3月 活動レポート/ウガンダ】
こんにちは。テラ・ルネッサンス ウガンダ駐在フェローの鈴木です。
これまでインターン時代とあわせて約一年間ウガンダに駐在していましたが、今月をもってテラ・ルネッサンスを卒業します。
これに伴い今月の月次レポートでは、私が一年間のウガンダ駐在を通して見てきたこと・感じてきたことを皆さんに共有させていただければと思います。
目の当たりにした世界の不平等
ウガンダ北東部にあるカラモジャ地域は、貧困や飢餓が深刻な地域でした。
2022年、カラモジャ地域では飢餓やそれに付随した病気、そして食料不足に起因する食料の強奪等を目的とした低強度紛争の被害を含めると3,000人以上が命を落としていました。
同地域内にある事業地のコティド県では同年、飢餓や飢餓に関連する病気等により1,600人が亡くなっています。
私がウガンダに駐在してからも、カラモジャ地域で起こる餓死、食料強奪等をはじめとする低強度紛争に関するニュースは頻繁に耳にしました。
実際、私たちの支援対象者にも、事業開始前の調査時には深刻な貧困状態に陥っていたり、病に苦しむ人々がいました。
生まれた場所が違うだけで、救える命・失われてしまう命があることを肌で実感し、やるせなさや、先進国に生まれた自身の生い立ちに引け目を感じました。
【支援対象者の親戚の男の子:
事故で足に銃弾が当たってしまうも、治療費が足りず十分な治療を受けられていませんでした】
「開発から取り残されてきた地域」への誇り
カラモジャはウガンダ国内やアフリカの中でも「開発から最も取り残された場所」として知られる地域で、先に述べたような実態があることは揺るぎない事実です。
しかし、そんな課題が多く語られる裏には地域に生まれたことに誇りを持ち、強くたくましく生きる人々がいます。
私たちは本事業を開始する前に支援対象者150人全員に「あなたがこの地域について誇りに思うことは何ですか?」といった質問をしました。
すると半数近くの方々が地域の文化について言及しました。
実際、大変な農作業が続くなかでも歌を歌ったり、踊ったりしながら活き活きと農業に励む彼女たちの姿を見てきました。
事業1年目が終了した日に行ったセレモニーで、150人全員が同じ場所で踊った時に感じた彼女らのパワーは壮大でした。
(セレモニーの様子についてはこちらの記事をご覧ください。)
彼女たちの文化を誇る気持ち、そしてその気持ちがもたらすパワーに魅了されながら共に過ごす日々は、私にとってとても刺激的でした。
「平和をつくる仕事をする」ということ
私はウガンダに駐在するにあたり、
“ウガンダで平和のつくり方を学び、自分なりの平和のつくり方を模索する”
という目標を掲げていました。
この「平和のつくり方」について、特に現場社会に根付いた活動を行うためには、
特に以下の2つが重要であると考えます。
①その地域をとりまく環境や社会、そして一人ひとりについて常に知ろうとすること
②一人ひとりに内在する未来をつくる力を信じ、誠実に向き合う姿勢
これらは当会の活動理念にも通ずることであり、どれも当たり前のことのように聞こえてしまうかもしれません。
しかし文化や習慣も異なり、様々な困難がある支援の現場でこれを貫くことは決して容易ではありません。
それでもこの2つをもって現場社会を知り、支援対象者に向き合い、現地スタッフらと試行錯誤しながら一歩一歩を進めるその先に、地域の平和があるように思います。
そして私も近い将来、そんな仕事をしにまたアフリカに帰ってきたいという強い想いを抱くようになりました。
今後は休学した大学に戻り、一年間肌で感じてきたことを、学術的な視点で振り返りながら、
ウガンダで見つけた新たな目標に向け、できることを積み重ねていこうと思います。
【一年間活動を共にしたカラモジャの現地スタッフたち:
最後にメッセージカードや、カラモジャの伝統衣装をプレゼントしてくれました】
======
記事執筆/
海外事業部 ウガンダ事業 フェロー
鈴木 千花

.png)
.png)
.png)