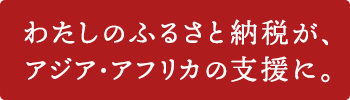【ハンガリー・ウクライナ】歩き、願い、祈る:マリアポーチ、4年目の夏
【2025年7月 活動レポート/ハンガリー・ウクライナ】
.png)
7/19〜20にかけて、テラ・ルネッサンスのハンガリー事業地の1つである東部マリアポーチ村へ出張に行ってきた。今回の出張の目的は大きく2つ——ウクライナ・ザカルパッチャ州から徒歩で巡礼に来る提携団体ギリシャ・カトリック教会(カリタス)の神父および信者の皆さまのサポートと、テラ・ルネッサンスがマリアポーチ村に設置しているウクライナ難民滞在施設の近況確認である。
徒歩での巡礼といえば、仏教のお遍路、キリスト教のサンティアゴ・デ・コンポステーラ(スペイン)巡礼、イスラム教のアーシューラーにおけるカルバラー(イラク)巡礼といったものが思い浮かぶが、テラ・ルネッサンスの活動地であるハンガリー・ウクライナにも同様のものがある。それが今回視察したザカルパッチャ-マリアポーチ間の徒歩巡礼である。マリアポーチ村には、大天使聖ミカエル教会というギリシャ・カトリック教会のハンガリーにおける総本山と呼べる教会が位置し、そこの信者は毎年徒歩でそこへ向かい、大規模なミサを執り行う。その歩行距離は、ハンガリー・ウクライナ国境のザーホニ市から数えても片道60kmを超え、フルマラソンの距離を上回る。
19日、ブダペストから車でマリアポーチ村へ向かったわれわれテラ・ルネッサンスは、途中大型スーパーで巡礼者に配る水を200本近く購入してから、午後4時頃にマリアポーチ村に到着した。前日の18日からウクライナ領内で徒歩を開始したカリタスご一行も、ちょうどこの時間に大天使聖ミカエル教会へ向かう最後の歩行を開始していた。
.png)
【聖歌を歌いながら大天使聖ミカエル教会へ向かうカリタスご一行】
道端に立ち、ペットボトルの水を巡礼者に渡していく。巡礼者の世代は子どもから高齢者まで幅広く、中には松葉杖や車椅子を使用しながら巡礼に励む方もいた。身体が万全でないながらも巡礼に参加するということは、(信者としての義務感もあるだろうが)この巡礼は大天使聖ミカエル教会に向かうこと以上の目的を有したものだろうということを、非キリスト教徒である筆者も肌で感じた。
午後6時半頃にミサが終わり、夕食を取りながらカリタスのペーテル神父とこれからの支援について話し合った。9月には、テラ・ルネッサンスがカリタスと協力し、ザカルパッチャ州ベレホヴェ市で建設している総合福祉施設が完成する予定だ。同施設はキッチンポイント、礼拝堂、多目的ホール等を有し、地域住民の安らぎと癒しの場を目指していく。テラ・ルネッサンスおよびカリタスの予算がともに限られている中、どのように最大限の支援を行っていくか・・・検討はまだまだ続く。
.png)
【これからの支援について検討する弊会ハンガリー事務所長コーシャ(右手前)とペーテル神父(右奥)】
翌20日、午前10時に教会前の広場でミサが始まった。ペーテル神父曰く、これが巡礼のメインイベントだという。筆者はハンガリー語を解さないため、「アーメン」以外は何を言っているのか全くわからない。しかし、聖歌を歌い、十字を切るカリタス信者を見ながら、テラ・ルネッサンス創設者である鬼丸昌也のある言葉を思い出した。
鬼丸は「願いは祈り」と職員に向けてメッセージを発することがある。筆者はテラ・ルネッサンスの一職員として、この言葉を以下のように解釈している。テラ・ルネッサンスは「すべての生命が安心して生活できる社会(=世界平和)の実現」を目的(ビジョン)に掲げている。ビジョンは一生かけて追求するものであり、現実とはギャップがあるのが当然である。むしろ、ギャップがあるほうが望ましいといっても過言ではなく、だからこそ願いをエネルギーに変換し、日々祈ることで一歩一歩、世界平和へ向かうのだ、と。宗教儀式に自身の考えを呼び込みながら臨むことには賛否両論あるだろうが、筆者はそのようなことを考えながら、ミサに参加していた。
.png)
【ミサの最後、神父たちの行進を待つ巡礼者ご一行】
12時頃にミサが終わり、テラ・ルネッサンスはカリタスと別れ、マリアポーチ村に設置しているウクライナ難民滞在施設を視察した。この施設は元々ゲストハウスであり、オーナーのご協力の下、現在もウクライナ東部から避難した10名程度の難民が暮らす。
.png)
【ウクライナ難民が滞在するマリアポーチ村のゲストハウス】
今回の訪問では難民の方に直接お会いすることはできなかったが、2022年のロシアのウクライナ侵攻当時、東部ドニプロからマリアポーチ村へ避難し、昨年ウクライナへ戻ったアーニャさん(仮名、30代女性)がたまたまゲストハウスに遊びに来ており、話をすることができた。ハンガリーでは昨年に難民関連法が改正され、アーニャさんのような若いウクライナ難民はハンガリーの滞在資格を失い、帰還を余儀なくされた。現在はドニプロで自身の小さい子どもと暮らす彼女は、いまだにドニプロや首都キーウで爆撃があること、子どもが通う学校に被害が及ばないか心配であることなどを英語・ロシア語・ウクライナ語を織り交ぜて語った。筆者はどの言語も程々にわかるので、彼女の発する言葉に一種の心地良さを覚えた。
以上がロシアのウクライナ侵攻から4年目を迎えたマリアポーチ村のひとつの光景である。徒歩巡礼という非日常と、村民とともにウクライナ東部からの難民が暮らしているという日常——「ハレ(非日常)とケ(日常)の間に人間は生きるのだ」と、村のところどころに咲くヒマワリの花が筆者へ語りかけている気がした。
---------------------------
記事執筆
海外事業部 ハンガリー事務所
田嶋 望